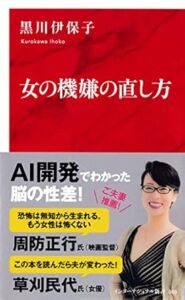
男女の間の意思疎通の隔たりは一体どこからくるのか?ということを、人工知能研究者の観点で解説した書籍の紹介と感想です。
この人の本を知るようになったきっかけは、数年前に見たNHKスペシャルです。
「妻が夫にキレる本当の理由」という特集で、夫婦間のいざこざを「ホルモンの違い」という観点で追求した内容でした。
ニッポンの家族が非常事態!? 第2集 妻が夫にキレる本当のワケ
奥さんがなぜ夫に怒るのか?そしてその理由は何なのか?ということや、それは実は分泌されるホルモンの違いによって生み出されるということ、さらに「脳梁の太さの違い」ということもがクローズアップされており、そこで初めて「脳の差」が考え方や行動の違いに出てきているのだなという知識を得ることができました。
その関係でネットで色々と調べてみて見つけたのが、今回の著書「女の機嫌の直し方」です。
一読してみて、それまでに感じたことがなかった「男女間の争いの原因は、持って生まれた脳機能の差」という観点でまとめた内容と、著者のユーモアあふれた文体に引き込まれ、一度ならずとも二度、三度と繰り返し読みかえしてしまいました。
とにかく内容が興味深く、「おおお」と感心したり「なるほどなあ」と納得したりすることが多く、ぜひこの書籍をブログで取り上げて、その論旨を自分なりにまとめてみようと思ったのが、今回の記事作成のきっかけです。
著書の要点のまとめと、最後に私なりの感想や実体験からの思いを語らせてもらいましょう。
Check!!男性ロックスター腕時計まとめ
Check!!女性ロックスター腕時計まとめ
*本サイトの記事内に広告が含まれる場合があります
男女の脳の差とは?
黒川さんの語る「男女の脳の差」とは何か?
それを端的に示した言葉が以下にあります。
左脳と右脳の連携の違い
人間の脳には「右脳」と「左脳」に分かれています。
それぞれに機能の違いがあって、右脳は「感じる領域」で、左脳は「顕在意識(思考)と直結して言葉を作る領域」。
この右脳と左脳の連携が良い脳は、感じたことがどんどん言葉になって意識に上がってきます。
女性はこの連携が良く「察したり、臨機応変に物事に対応できる」理由がここにあるといいます。
一方、右脳と左脳の連携がそれほどではない脳は、空間認知力が高いということ。
その特徴は「遠くから飛んできたものに瞬時に照準が合い、構造物を組み立てるのが得意」ことにあります。
この脳が男性に特有のもので、目の前の細かいことには目がいかないけれども、遠くのものは目に入る、ということにつながるというのです。
この左右の連携の違いは、脳と脳をつなぐ脳梁の太さに起因しているといわれ、そのことは先ほど挙げた前回のNHKスペシャルでも取り上げられていました。
脳梁とはいわば神経線維の束で、この束が生まれつき女性のほうが太いといわれています。
こうした脳の連携の違いによって、男女の思考や行動様式に違いをもたらすのです。
ポイント
女性⇒察する能力が高い、臨機応変に対応できる
男性⇒空間認知能力が高い、構造物を組み立てるのが得意
問題解決の取り組み方への男女の違いとは?
脳の連携の差が男女の行動様式に違いをもたらすことが分かりました。
ではそれが実際の業務や生活上での問題解決への取り組みに、どのような形で反映されているのでしょうか?
こちらも著者は端的な言葉で以下のように説明していました。
女性⇒プロセス指向共感型
男性⇒ゴール志向問題解決型
女性の「プロセス指向共感型」というのは、一言で言えば「共感しながら文脈を紡いでいくこと」。
女性脳は、ある事柄を語るときは、その過程(プロセス)を語るうちに、そこに潜む真理や真実を探る作業を行うといいます。
この過程で「思う存分に」その経緯を思い出すこと、そしてそれをリアルに再体験することで状況認識を行うのです。
そこで行っていけないのは「話の腰を折ること」。
女性は事の発端から時系列に経緯を語りながら、真実や真理を探しているので、この作業を中断されると、それまでの思考の積み重ねが無為に帰してしまい、再開はほぼ不可能になってしまうのです。
そしてそれが女性にとっての「不快感」につながるということ。
この過程をスムーズに行うために必要なのは「共感してあげること」だといいます。
話しながら答えを見つけるために、その過程で共感をもって上手に話を聞いてあげると、この作業の質があがり、話し終えるころにはきっぱりと結論が出ているというのですね。
一方の男性は「問題解決のために」対話を行います。
相手が状況を語りだしたら、その対話の意図を探り、すばやく「解決すべき問題点」を洗い出そうとするのです。
優秀な男性ほど「省エネ型」で、枝葉末節に心を乱されることなく、全体の構造をシンプルにとらえようとする傾向があること。
これは先ほど取り上げた「遠くから飛んできたものに瞬時に照準を合わせる」脳の構造に起因すると著者はいいます。
長らく狩りを担当してきた性から発達したものだと仮定しており「全体を俯瞰して、ものの位置関係と距離感を正確に把握する」ことにつながるとも触れています。
依怙贔屓をしないこと、世界を把握して経済を動かすこと、獲物を獲得したり、複雑な機構を組み立てたり、ビルを建てたり、飛行機を飛ばしたりするために「公平性」を男性は獲得する必要があるということ・・・
男性は自分の心情よりも、公平性を順守する脳を持つということなのですね。
この脳の差が、対話のスタイルにも如実にでており、それが女性の「共感してもらいながら、事の発端からプロセスを語り、その中で真実を探り出す」、男性の「問題解決のために、問題点を素早く洗い流し、結果を出す」という真逆の形になって表れているということなのです。
ポイント
・女性の対話スタイル⇒共感をもとに対話を紡ぐ
・男性の対話スタイル⇒問題解決のために結論を先に紡ぐ
脳を活性化するための「男と女」それぞれの方法とは?
脳の活性化のプロセスにも、男性と女性の差があります。
これを端的にまとめた言葉が以下になります。
男性は、ぼうっとしているときに頭がよくなる
女性は、心地よい気分になると脳が最大限に活性化される
まず男性についてです。
空間認知力を究極にまで使うと、左右の脳の連携がほぼゼロになります。
これは「感覚器からの情報(右脳)」が「顕在意識(左脳)」に上らないということ。
つまり脳を最大限にフル回転しているときは、ぼうっとしている状態になるということになります。
たとえばテレビのチャンネルをつけながら、見ているとも見ていないとも分からない感じでぼうっとしている時とかは、それまでの知識を脳の中で整理整頓している作業でフル回転している時ともいえるのです。
こうした「ぼうっとした時間」がない男性は、世界観の狭い、戦略の立てられない男になってしまうということ、学生なら理系の能力が伸びないということにつながると著者は言います。
こうした男性の「ぼうっとした時間」を脳神経回路の使い方でみると、同様の神経信号は禅の修行や、写経、華道、茶道、剣道の形の稽古のような「完成度の高い形をなぞるシンプルな動作の繰り返し」でも起こるということ。
つまり、意図的に脳の左右連携を絶つ行為が、そうした「~道」に代表される伝統芸の目的の一つであり、空間認知能力を活性化して、世界観や直観力を養う大事な脳のエクササイズであるということにつながるのですね。
目の前をアリが通り過ぎても、網膜が黒い点と捉えても、アリと認識しない状態。
寒くも暑くも、痛くもかゆくもない世界。
著者がある高僧に「無我の境地」について聞いた見解だそうです。
これを聞いて「男性のぼうっとする時間と同じだ!」と思ったといいます。
左右の脳の連携が密接な女性であれば、黒い点を網膜に移った瞬間にそれは「アリ」であり、次の瞬間にアリ塚の方向を察知し、残り物のお菓子がテーブルの上にあったことに気づいて走り出す・・・それが女性脳だと。
それくらい女性によっては「無我の境地」は難しいということ。
とはいえ、女性には女性の脳の活性化の方法はあるのです。
それが「気持ちのよいこと」。
美味しいものを食べ、エステティックに行って、心地よい皮膚感覚をもらうと、脳が最大限に活性化されるのだそう。
もちろん女性にも左右の脳の連携を絶つことの意味はあります。
左右連携が強すぎると、人の思惑が気になり、自分を見失ってしまいます。
近視眼的になり、世の中のありようを理解できなくなるので、常に他者と気持ちがすれ違うようになってしまう・・
そんな状態の脳の左右連携を断つために、女性にとっておすすめなのが「瞑想」だといいます。
心地の良い音楽を聴いたり、マントラに導かれて行う、ヨガも良いようです。
他にもエステに行ってマッサージをしてもらい、眠っていただけではないのに、何も考えていない時間があったならば、それが「左右の連携を絶って脳を活性化した状態」であるということ。
女性にとっての「脳の活性化」のポイントは「心地よさ」に尽きるのでしょうね。
ポイント
・男性の脳の活性化の方法⇒「ぼうっとする」こと
・女性の脳の活性化の方法⇒「心地よいことをする」こと
まとめ
以上が著書を読んで最も印象に残ったポイントになります。
全体的には「男性と女性の脳の差」、そこから発展した「対話及び思考形式の違い」、さらにそこから発展した「両者の問題解決の違い」、そして最終的には「それぞれの脳の活性化方法」という流れで、今作の著者の主旨の骨格を捉えたつもりです。
今回の著書で一番面白かったのが、「男性の脳は問題解決型で、女性は共感を基に対話を紡ぐこと」というくだり。
私はこれまでの人生で女性を怒らせたり、呆れさせたことは無数にあるのですが(汗)、それらのほとんどが著者の言う「共感のなさ」からくるものだということを知り、「ああ、あのときこうやって接してあげればよかったのか・・」と反省するに至りました。
物事の経緯や、結論の多くは私の考えでも別段悪くはなかったのですが(自分でそう思っているだけかもしれませんが苦笑)、そこに至る対話のプロセスといいますか、相手の意見を途中でぶった切って「だからこういうことだろ?だったら~でいいじゃないか」という形で結論に至らせてしまったケースが多かったということ。
これはまさに黒川さんのいう「女性は共感してあげることで真実を紡ぎだす」「女性は問題解決は自分でする。経緯を語り尽くしたのに、どうしても答えが出ないときだけ、救いの手を必要とする」であり、こういう時は「最後まで気持ちよく会話の着地まで付き合ってあげる」ことが大切だったのだなあ、と遠い目をして過去のあれこれを思い出しておりました^^;
逆に言えば、男性的には本書の要点はそこに全てが詰まっているような気がしますし、女性にとっても、男性の「脳の違いと思考形式」を知ることで、男女間のストレスの軽減に役立つように思います。
まあ多くは我々男性が気を使わなくてはならないことなのでしょうがね^^;
他にもたくさん面白かったり、参考になった内容がたくさんあるので、本を実際に買って皆さんの「女性への理解」の参考にしてみてください。
デートスタイル
関連まとめ














